おうちコリア留学です🏠🌼
韓国の大学院進学を目指し、おうちコリア留学のサポート利用される方が増えています
大学院進学で、もっとも重要な「研究計画書」の内容に悩んでいる、作成はしているもののプロに添削してもらいたい…
と利用理由はさまざまですが、合格される方は弊社サポートを利用し徹底的に対策されています
そこで「研究計画書の書き方」と題し、おうちコリア留学の大学院準備のノウハウの一部をご紹介します!
(シリーズ化となるので、SNSをフォローして最新記事をチェックできるようにしてくださいね
第1弾の研究内容が全く決まっていない方向けの【研究内容を決めよう編】に続き
今回は研究計画書の必要性と方向性を決定づけるための【先行研究を分析しよう編】です🔍!
1. 「先行研究の分析」とは?
そもそも「先行研究の分析」とは何でしょうか?💭
「先行研究」とは各分野で、これまでに行われてきた研究のことを指します!
そして「分析」するということは、自分が研究しようとしている分野において
①過去にどのような研究が行われてきて
②どこまでが明らかになっているか
③どこが明らかになっていないのか
この3つを主に調べる作業です🔍
大学院は学部と違い、自分が所属する学術分野に新しい知見を提供し、その分野の研究者や先生と意見交換を行うことに重きを置いています。
つまり、すでに行われている研究と同じことをしていては新しさや独自性がありません🤔
先行研究の分析を通じて自分の研究の必要性と独自性を主張し、研究の方向性を決めていきます🚩
先行研究の分析では、かなり多くの論文を読む必要があるため、気が遠くなる作業に感じられるかもしれません…が!
この分析が今後の研究を左右するといっても過言ではないので、しっかり取り組みましょう🔥
2. 分析の仕方
先行研究は大きく3つの視点から分析する必要があります👀
①疑問に思っていることについて調べる
研究テーマを決めるときは自分の実体験などから疑問を持ち、それを研究に発展させていくことが大切なポイントです。
その疑問点がすでに研究によって明らかにされ、答えが出てしまっている場合は研究を進める意味(=必要性・独自性)が薄れてしまいます🌀
そこでまず「自分が抱いている疑問はすでに解消されているのか」を調べましょう!
この段階ですでに答えが出ている場合は、別の視点から疑問を立て直す必要があり、場合によっては研究テーマ自体を大きく変更しなければならないこともあります。
同時に他の研究でも同様に課題や問題として挙げられているのかもチェックします。
そうすることで「自分の疑問は個人的な関心ではなく、この分野全体の課題として共有されている=研究するに値するテーマである」と客観的な根拠を示すことができます💡
②疑問に対して過去にどのようなアプローチがあったのかを調べる
次に「疑問に対して過去の研究ではどのようにアプローチしたのか」について調べます🔍
ここでいう「アプローチ」とはどんな理論や方法を使って問題を明らかにしようとしたのかを指します。
この段階では、
①どのような対象を扱った研究か
②どのような方法でデータを集めたのか
③どのような観点から分析を行ったのか
を整理しておくと、後で自分の研究方法を決める際に大いに役立ちますよ✨
また、研究は「1+1=2」のようにひとつの答えが出る世界ではありません!
同じテーマでも、研究者によって理論的立場や分析方法、見解は千差万別🙏
「自分が抱く疑問はすでに扱われているけど、この視点(理論・方法)からなら新しい見方ができるのでは?」という発想が非常に重要になります🙂↕️
過去の研究の「どの部分を引き継ぎ、どの部分を変えるのか」を明確にして、独自性のある研究につなげていきましょう🚀
③アプローチによってどのような結果をもたらしているのかを調べる
次に「各研究で用いられたアプローチによって、どのような結果が得られているのか」を確認します。
これは単に「結果の内容」を知るだけでなく、
①どんな条件で効果が見られたのか
②研究者がどのような課題や限界を指摘しているのか
を丁寧に読み解くことがポイントです📚
特に「限界(=今後の課題)」の部分は重要です。
たとえば、
「既存研究では中級学習者を対象にしていたが、初級学習者に適用した研究は少ない」
「会話能力に焦点を当てていたが、学習者の自信(自己効力感)までは扱っていない」
といった指摘を見つけられれば、そこから自分の研究テーマをより具体的に設定できます💬
さらに、結果を比較してみることで、研究者によって結論が異なる部分(=まだ議論が分かれている部分)も見えてきます。
そのような部分こそが新しい研究の「伸びしろ」としてアピールできます🌱
3. 分析するときのポイント
分析するときは、ただ論文を読むだけではなく、以下のポイントを押さえながら整理していきましょう📝
✔️明らかになっている点とそうでない点を明確にする
自分が研究しようとしているテーマについて、現在どのくらい研究が進んでいるのか(現況)を把握する作業です!
この段階で、自分の関心と先行研究の内容を照らし合わせながら、まだ十分に扱われていない部分や別の視点で掘り下げられる可能性を探します。
たとえば、「対象が限定されている」「特定の変数が考慮されていない」「時代背景が変わっている」など、研究課題のギャップに注目すると新しさをアピールできます💡
研究は常に更新されているので、できるだけ直近5年程度の論文を中心に調べるのが理想的です👏
場合によっては、理論の変遷を追うために10年ほど遡ることもありますが、基本的には「最近の研究を軸に現況を把握する」意識を持ちましょう。
✔️学術論文を使用する
「学術論文」とは、その分野や学会に所属する研究者が内容を厳しく審査された上で、学術誌に掲載された研究成果のことを指します。
論理の一貫性・方法の妥当性・結果の信頼性などがしっかり確認された信頼できる情報源です。
一方、書籍は著者の経験や意見をもとに比較的自由に執筆できるため、理論の裏付けが弱かったり主観が強く出る場合もあります🧐
もちろん、研究の背景を理解したり入門的な知識を整理したりする上では書籍も有用ですが、先行研究の分析では大学図書館のデータベースや学会誌を活用しながら、信頼度の高い「一次資料(学術論文)」を中心にとらえることが大切です。
✔️指導予定教授の論文は要チェック
先行研究を分析する際は志望大学院の指導予定教授の論文を必ず確認しておくことも重要です!
教授がこれまでどのようなテーマ・理論・研究方法に関心を持っているかを理解することで、自分の研究との共通点や方向性の一致を見つけやすくなります。
教授の研究分野と自分のテーマを関連づけることによって「この教授のもとで研究を深めたい」という志望動機にも説得力が増します。
実際に研究計画書では「教授のどの研究と関連があるのか」を明示することで、研究の具体性が高まり選考時の印象も良くなります✨
✔️韓国語以外の論文も調べる
「韓国の大学院に進学するから論文は韓国語のものだけ読めばいい!」と思いがちですが、実際はそうではありません。
自分の研究テーマに関する先行研究は、韓国だけでなく他国でも活発に行われていることがあります🌎
たとえば日韓比較が含まれる研究では、日本で発表された論文、研究の基礎となる理論は英語で書かれた論文の中に重要なヒントが隠れていることも…!
韓国語だけに限定せず、日本語・英語・その他研究対象となる地域の言語の論文も視野に入れることが、より広い視点から研究を進める鍵になります🔑
【主な論文検索サイト】
・韓国語の論文
RISS:https://www.riss.kr/index.do
KCI:https://www.kci.go.kr/kciportal/main.kci
SCIENCE ON(理系):https://scienceon.kisti.re.kr/main/mainForm.do
・日本語の論文
CiNii:https://cir.nii.ac.jp/
・多言語
Google Scalar:https://scholar.google.com/
※一部有料で日本から支払いができない場合、抄録(Abstract)だけでもチェックすること✅
※CiNiiで非公開でも国立国会図書館に論文の複写依頼することが可能💡
※参考にした論文はリストにしておきましょう(書き方例:著者名(年度)、論文タイトル、『学術雑誌名』巻号、出版学会、ページ数)
4. まとめ
では、1~3に挙げた内容を次の研究内容を例に考えてみましょう👩🎓
【テーマ】
日本人学習者対象の劇を使った韓国語会話教育の提案
【背景】
・日本人学習者は韓国語で会話することに不安を覚える
・この不安を取り除くためには実践力が必要なんじゃないか?
・そのためには実際のシチュエーションを想定した劇を通じて会話練習をする必要があるんじゃないか?
・日本ではそのような教育は行われていないのか?
・「実際のシチュエーション」とは何か?(円滑なコミュニケーションを構成する要素とは?)
先行研究①:自分の実体験を元に気づいた問題点について
→複数の研究者が「日本人は外国語で話すことに不安を覚えている」「ヨーロッパ諸国の学生よりも外国語でのコミュニケーションに対する不安感が大きい」という結果を提示している。しかし、それに対する教育方針は提示されているものの、その不安を軽減するための具体的な教育課程や授業設計、学習活動の構成方法までは示されていない(강소산(2018), 김유선(2019), 朴恩珠(2020)など)。
➡したがって、「外国語学習における不安の低減」を目指した実践的な教授法・教材開発が今後の課題として残されているといえる。
先行研究②:これまで行われてきた劇を使った会話教育の効果について
→語学堂や日本の大学において、学生自身が脚本を考えたり、既存のストーリーを改編して劇を行う授業が実施されており、「雰囲気に没入できて楽しかった」「協同学習を通じてコミュニケーション能力が向上した」といった効果が報告されている(주현주(2020), 金世朗(2023)など)。特に、即興的なやり取りを通じて学習者の発話を自然に引き出すプロセスドラマ(過程劇)は、会話力の向上や学習者の自発的な発話促進に効果があると考えられている(Heathcote & Bolton(1995), 이정희 외(2018)など)。しかし、既存研究の多くは授業実施後の効果検証が十分に行われていないことや、劇の内容が非現実的で実生活の会話場面との関連性が弱いという問題がある。
➡したがって、プロセスドラマの教育的効果を実証的に検証しつつ、実生活での言語使用に直結する内容を反映させた教育課程の設計が今後の課題として残されている。
先行研究③:日本での韓国語教育について
先行研究④:円滑なコミュニケーションを構成する要素について
先行研究⑤:・・・
このように、2で挙げた視点から複数の疑問点を整理・分析していきます。
分析の際は3で示したポイントを意識しながら、各項目につき5本以上、合計で約30本以上の論文を読み、内容を整理します🧹
この作業を通して、自分の研究で何を明らかにすべきか、どの方向性で研究を進めるべきかが明確になりました🙆♀️
このあとに行うのは「研究方法選定と意義のアピール」です。
研究計画書は「入学後すぐにこの研究に取り組めるほど具体的な計画があります」ということを示す重要なアピール文書であり、合否を決定づける書類です📃
そのため研究方法もある程度、具体的に固めておく必要があります。
この研究が社会にどのように貢献できるかを明確に示すことで、研究の意義や必要性も併せて主張することが求められます👏
次回の記事では研究計画書のまとめ【研究方法と意義のアピール編】をお届けします😉
先行研究の整理や研究計画書の書き方はもちろん
「自分ひとりで書いたけど誰かに見てもらいたい…」「もっと具体的なアドバイスが欲しい…」「韓国語文の表現などは合ってるかな…」という方は
ぜひ、おうちコリア留学の「添削サポート」をご活用ください👌
✔️ 自己分析シートを用いて志望動機を振り返り
✔️ 研究計画書/自己紹介書に書く内容を整理
✔️ 作成した文章を添削
✔️ 韓国語ネイティブチェック
研究計画書を「ただ書くだけ」で終わらせず、自分自身の強みをしっかり反映させたい方におすすめです😌
大学院生活に関する記事はこちらから💁♀️
おうちコリア留学カウンセリング
「韓国の大学院についてもっと知りたい!」という方はまずカウンセリングサポートをご利用ください✨
韓国留学経験のあるスタッフが丁寧に個々に合わせたカウンセリングをいたします!
おうちコリア留学のLINE公式アカウントをお友達に登録して
「カウンセリング希望」と送信してください💌
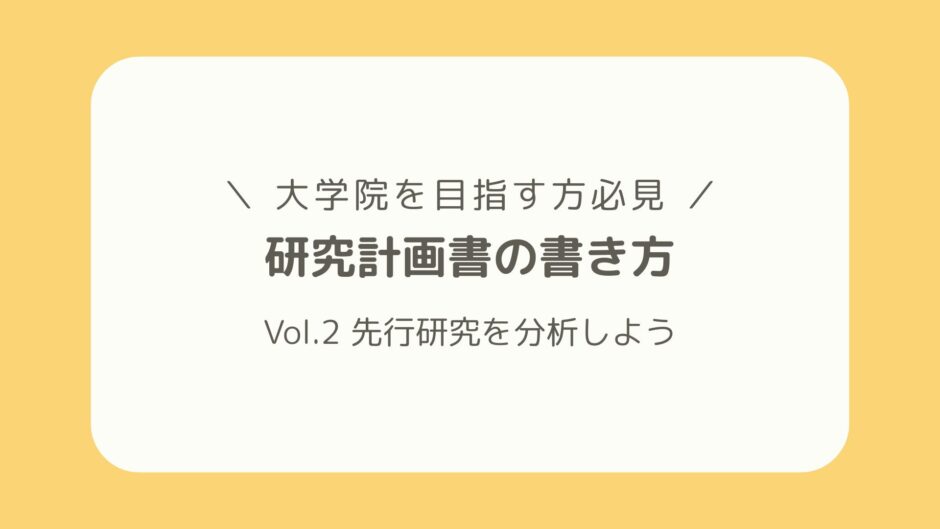



-1-160x160.jpg)